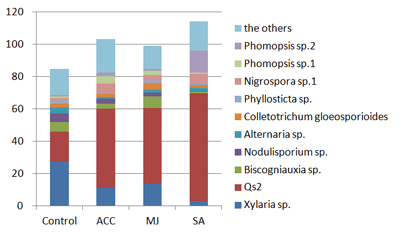【研究紹介】謎の多い内生菌の特性を新たな手法で解明する
|
楠本 大(森林生物機能学研究室/田無演習林 助教) |
研究内容 |
|
植物と菌類との関係は古く、そして複雑です。例えば、植物の根と共生して、植物から光合成産物を受け取る代わりに、土壌のミネラルを植物に渡すような共生菌もいれば、生きた植物の中に入り込み、植物の一部や全体を殺してしまうような病原菌もいます。生きた植物は利用できず、枯れた植物遺体を分解して栄養を摂取する腐生菌もいます。共生・寄生・腐生といった植物と菌類との多様な関係が存在する中で、近年注目されているのが「内生菌」と呼ばれる菌類です。 内生菌とは、外見上は病徴がなく健全にみえる植物体の中で生存している菌類のことで、植物に普遍的に存在しています。最初に注目されたのは牧草などイネ科草本と共生するバッカクキン科の内生菌で、内生菌のいる牧草を食べた家畜が中毒を起こしたことから有名になりました。バッカクキン科内生菌は毒素を生産し、植物の病虫害抵抗性や環境ストレス耐性を高めることが知られています。 一方、樹木の葉からも多種多様な菌類が見付かっています。そのほとんどは糸のう菌類で、非常に幅広い分類群から見付かっています。樹木の内生菌は、広い宿主範囲を持っている種が多く、周囲の環境条件や供給される胞子量などによっても大きく感染率が変化することから、宿主―内生菌の相互関係に一定の傾向を見出すことが難しいとされています。そのため、どの内生菌種がどのような生態学的機能を持っているかはほとんど明らかにされていません。 我々は、宿主―内生菌の相互関係の一端を明らかにするため、植物の病害抵抗性遺伝子を発現させるサリチル酸、ジャスモン酸、エチレンといったシグナル物質をコナラの葉に処理し、内生菌の種構成の変化を調査しました。その結果、シグナル物質を処理した葉と処理しない葉では、内生菌全体の分離率は大きく変わらないものの、種構成は大きく変わり、増加する菌と減少する菌があることが分かりました(図1)。このことから、増加した菌は宿主の防御応答に耐性を持つこと、減少した菌は耐性は弱いが、宿主に認知されないように感染している可能性があることなどが予想されました。また、増加した菌と減少した菌の関係から、この両者間には競争関係があることも予想されました。加えて、環境ストレスが宿主の生理状態を変えることによって、内生菌の種組成が変わる可能性も示唆されました。 シグナル物質を使ったこのような研究手法は、内生菌ではまだ例がありませんでした。今回の結果から、宿主の生理状態を人為的に変化させる方法は、宿主―内生菌の相互関係や内生菌の機能を明らかにする糸口をつかむのに有効な手法であることが示されました。 |
図表 |
|
|
発表文献 |
| Kusumoto D, Matsumura E (2012) Effects of salicylic acid, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid and methyl jasmonate on the frequencies of endophytic fungi in Quercus serrata leaves. Forest Pathology 42:393-396. |