| 台湾研修報告 澤田晴雄(愛知演習林)・大屋一美(北海道演習林) ・村川功雄(千葉演習林) ・千嶋武(田無試験地) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はじめに 2006年3月23~26日に台湾を訪れ、主に台湾大学実験林と台湾林務嘉義林区管理所阿里山森林遊楽区で実践されている森林の観光利用の実態を視察研修してきた。今回の目的は台湾大学実験林ならびに阿里山森林遊楽区における事業の展開を把握し、東京大学演習林の現状との比較を行い、その上で東京大学演習林に必要な事業や活動を検討することである。また今後の本研修や台湾大学実験林との交流に対する意見や提言などについてもとりまとめて報告する。 1. 日程 ○2006年3月23日
○2006年3月24日
○2006年3月25日
○2006年3月26日
2. 台湾 台湾は日本の南西にあり、南北に長い島で面積は36,000k㎡、九州よりやや小さい。人口は約2,300万人。首都は台北で、人口は約262万人。島の東側は南北に山脈が走り、最高峰玉山(3,950m)がある。西側は平野で豊かな農地が広がっている。島の中央を北回帰線が通り、高温多雨の熱帯性気候である。かつて中国清朝の領土であったが、日清戦争の結果、日本の領土となった。第二次世界大戦後、中国大陸から国民党政権が移ってきて台北を首都とした。先住民はマレー系高山族であるが、中国本土から移住した漢民族が98%を占める。農業がさかんで、米・サトウキビ・バナナ・パイナップル・茶などの栽培がおこなわれている。木材・鉱物資源も多い。近年は外国の企業が進出し、各地で重化学工業が発達している。 時差は日本より1時間遅く、例えば日本が正午のとき台湾は午前11時である。通貨は台湾ドル(元)で1元が約4円であり、物価は日本とあまり変わらない。 3. 台湾の動植物 台湾は、低地のうち北・中部が亜熱帯、南部は熱帯に属す。日本のようなはっきりとした四季はなく、1年は長い夏と短い冬があるだけで夏は暑くて冬も比較的温暖である。中央部には南北に連なる3,000m級の山脈があり雪積も見られる。 標高は0~3,952mと幅広く、熱帯から寒帯までの森林が分布しているため動植物の種類が豊富で、野生動物は約18,800種、うち哺乳動物が70余種である。また固有種の割合が約20%と高いことも特徴としてあげられ、希少種も多い。昆虫は18,000種以上、そのうち蝶類が約400種と多い。爬虫類・両棲類・淡水魚でも台湾固有種が多い。 台湾希少動物のうちで、もっとも知名度の高いのが「サクラマス」で、陸に閉じ込められたマス、また地球上きわめて稀な亜熱帯に生存している寒温帯魚として知られている。このほか台湾ザル・台湾クロクマ・キョン・ハクビシン・サンケイ・ミカドキジ・クロツラヘラサギ・ヤマムスメ・アオウミガメ・アカウミガメ・台北アカガエル・アオガエル・フトオアゲハ・アケボノアゲハ・コウトウキシタアゲハなど多くの種が固有種かあるいは台湾を含む数少ない地域でしかみられない貴重なものである。 植物の種類も多彩で、原生維管束植物は約4,000余種で、そのうち約1,000種が台湾固有種である。なかでも鳥来つつじ・玉山衛茅・大安水簑衣・台湾穂花杉・台湾粗榧・台湾杉などは台湾でしかみられない。 4. 台湾大学実験林の概要 ○概略 国立台湾大学実験林は、1901年東京大学(農学部)の演習林として設立された。その後、台湾政府の所有となり、1949年に台湾大学に移管された後、1950年7月に国立台湾大学実験林が発足した。 台湾大学実験林の主な目的は、1)アカデミックな研究、2)教育とフィールド実践、3)資源の保護、4)森林管理の実証の4項目である。 実験林の位置は台湾の中心にあって、行政的には南投県に位置し、標高はJhuoshuei川南岸の22m~Yushan(玉山=旧・新高山)の3,952mまで幅広い標高差を有し、面積は台湾の1%にあたる32,781haを占めている。この幅広い標高差により、亜熱帯・暖温帯・冷温帯・亜寒帯・寒帯の5つの気候帯が存在している。それぞれの気候帯には、東南アジアで最高のサイトと評価されている森林を所有しており、植物や野生生物資源も豊富で、たくさんの大学や研究機関から利用されている。 1996年の台風ハーブ、1999年の大地震、2001年の台風トラジなどの襲来によって実験林は壊滅的なダメージを受けた。ここ近年の再建は、市民に対して新しい実験林を提供する目的と「自然教育」の再編により国際的な発展に対応することを目指して計画された。 現在、台湾大学実験林は、政府政権、大学と関連した学会の再編成で新しい試練に直面し挑戦している。 ○台湾実験林の面積・年間降雨量・年間平均気温
○組織 台湾大学実験林は、Sitou・Gingshueigou・Shueili・Neimaopu・Heshe・Dueigaoyueの6つの地域に区分され、 2004年12月現在152名(研究者18名、専門家43名、管理者13名、技術者78名)で運営されている。 以下に組織図を示すが、これは1988年に管理規則の改定(7回目)時からのものである。 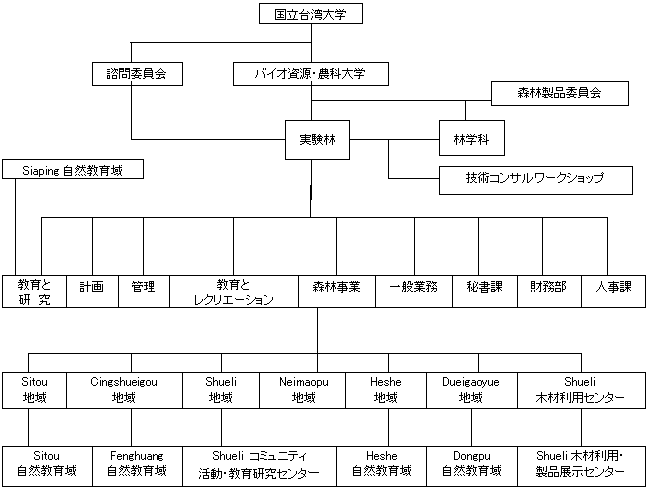
5. 台湾大学実験林の経営展開 台湾大学実験林の主な目的は先に紹介したようにアカデミックな研究、教育とフィールド実践、資源の保護、森林管理の実証の4項目であるが、私たちが訪れたSitou実験林は観光業に特に注力している。たとえば入園者だけでも年間100万人あり、入園料として大人一人一日200元(約800円)を徴収し、年間パスポートも発行している。また宿泊施設(ホテル、コテージ、山小屋)、製茶工場(茶畑もある)、民営売店の誘致などがあり、そうした収益の合計は年間約3億円である。 実験林は約150名足らずの職員で、研究・教育・森林管理・生産事業などの他に観光事業を行っている。そのことを可能にしている大きな要素として民間の力を活用している点が上げられる。実験林の入場施設、ホテルやコテージ、茶工場、製材工場の運営に請負や民間業者が関わり、実験林における観光業の中核を支えている。 6. 台湾林務嘉義林区管理所と台湾大学実験林との比較 日本で言えば森林管理事務所(旧営林署)に当たる台湾林務嘉義林区管理所での観光事業展開を台湾大学実験林のそれと比較するために視察した。場所は台湾大学実験林の南に隣接する阿里山国家森林遊楽区である。阿里山の中心地は標高2,200~2,300m付近にあり観光地・避暑地として国際的にも有名で、森林鉄道に乗って祝山山頂(標高2,489m)まで行き日の出を見るサンライズツアーの人気が高い。紅檜の巨木(樹齢800~2,000年)を巡る遊歩道やトレッキングコースなども完備され森林浴やトレッキングを楽しめる。また楓の紅葉やサクラ(主にソメイヨシノ)の花の名所でもあり、それらの季節には多くの観光客が当地を訪れる。なお阿里山遊楽区の入園料は大人一人一日200元(平日は150元)である。 阿里山は台湾大学実験林よりも更に民間活用による観光化が進んでおり、ホテルや民宿、民営売店があり、土産物やグッズなども豊富である。こうした業者と林区管理所が一体となり集客し、入園料やお土産用の木材生産・加工販売収入から森林の管理・運営費を稼ぎだしている。 7. 東京大学演習林と台湾大学実験林との比較 東京大学演習林での観光業もしくはそれに近い収入としては、最近始まった有料の公開講座や本や小冊子の販売くらいで、その金額は残念ながら微々たるものである。だからと言って台湾大学実験林や阿里山をモデルに、入園料の徴収や宿泊施設・売店などの民営活用を今すぐ導入したとしても成功しないであろう。 その最大の要因は森林あるいは入園料に対する意識と、利用者数の違いである。台湾は山が高くて険しく、河川勾配が急峻で、台風や豪雨が夏と秋に集中するため災害が甚大である。その一方で雨が暫く降らないと水不足にも陥りやすく、そのため自然災害を軽減するために森林を保全しようという国民の意識が高い。その上、国も保全する必要のある森林を積極的に守り、同時にレジャー区や遊歩道、公衆衛生施設などを整備して国民へのサービスを提供しながら森林保全に対する理解を深めようと勤めている。 また台湾では隔週週休二日制の実施により、市民がレジャーを戸外で過ごす機会が増え、各種レジャー施設の拡充が必要となっている。しかし、台湾は人口密度が多く現状では個人のレジャー施設を確保するのは困難であり、拡充も容易なことではない。また公共の森林レジャー施設の運営は行政上さまざまな制限を受け、さらに経費不足やサービス面など様々な理由から民営化の方向に向かっているのが現実である。 そうした背景からか、台湾では台湾大学実験林や亜里山のような森林を訪れることをとても楽しみに考えており、入園料を払ってでも訪れたいというニーズが存在し、事実、台湾大学sitou実験林には年間100万人もの入園者が訪れている。また徴収された入園料で森林が保全されているという理解も得られている。 一方、日本では森林に無料で入れるという意識が強いためか有料の森林施設は少ない。一例としてある森林公園(入園料400円)を上げると、そこでは森林だけではなくサイクリングコースや各種遊具を整備したり、梅園、福寿草園、コスモス畑など季節ごとの目玉となる見物を作るなどの努力をし、それでも前年の入場者数をようやく維持、あるいは微減しているのが現実である。 森林の観光利用だけでなく木材販売も含め、日本の森林に現金を還元することは非常に難しい現状にある。 8. まとめ 以上述べてきたように台湾大学実験林での事業展開をそのまま東京大学演習林に当てはめることはかなり厳しいと言わざるを得ない。しかし、その手法や考え方で参考になることを上げるとすれば、事業の全てを自分たちで実行しようとはせずに民間あるいは周辺市町村、別の団体が行ったほうが良いものは任せるということがポイントになると考える。 その一方で微々たる額ではあるが、ちょっとしたお土産や小冊子などの販売により、事実上入園料の代わりとすることも、やってみる価値があると思われる。昨年秋に千葉演習林で行った一般公開日での小冊子販売などがその一例であろう。森林の直接利用に限らないものを上げると、本やビデオの販売、林産物から作ったグッズの販売も視野にいれてもいいのではないだろうか。利益は薄くてもパッケージにホームページのアドレスや、いろいろなメッセージを書いて演習林の存在を周知する努力も、地味ではあるが必要なのではないかと感じた。 最後に、今後も台湾大学実験林と東京大学演習林の研修による交流が継続するのであれば以下の意見を参考にしていただければ幸いである。今回は日程が過密であり、体力的に大変であったのはもちろん、研修内容をまとめる時間がなく、残念ながら貴重な視察体験が消化不良気味になってしまった。同時に過密日程にともなう移動の負担(特に台湾大学実験林職員による自動車運転)が大きく、次回の研修はもう少し台湾大学実験林職員に配慮した日程を計画した方が良いと感じた。その上で希望を言えば台湾語の分かる人が一人随行してもらえると台湾大学実験林職員とも、もっと親交を深めたり色々な情報・意見交換が出来たと思う。そうした交流こそが台湾大学と東京大学にとって大きな意味を持つものと信じて止まない。 謝辞 今回、台湾で本当に貴重な経験をさせていただき、また見聞を広げることができ大変ありがとうございました。本研修を発案された東京大学演習林研究部長の丹下健先生、現地で同行していただき御足労をおかけした東京大学法学部教授のChen先生、現地での移動や案内をしていただいた台湾大学実験林の王亞男林長をはじめ実験林スタッフの皆様には本当にお世話になりました。この場を借りて厚く感謝申し上げます。 |





